

2022.11.22

日本史には沢山の謎があります。
その中でも最大の謎の一つとされているのが、「土偶」です。
縄文時代に土器が発明されて以来、人の形をかたどった土器として、およそ2000年前まで作られ続けました。
しかし、その目的は謎とされています。
今回は、日本語や考古学の知識をもとに推理を行い、土偶の謎に迫ってみたいと思います。
考古学的に解明されている事実をまず整理してみたいと思います。
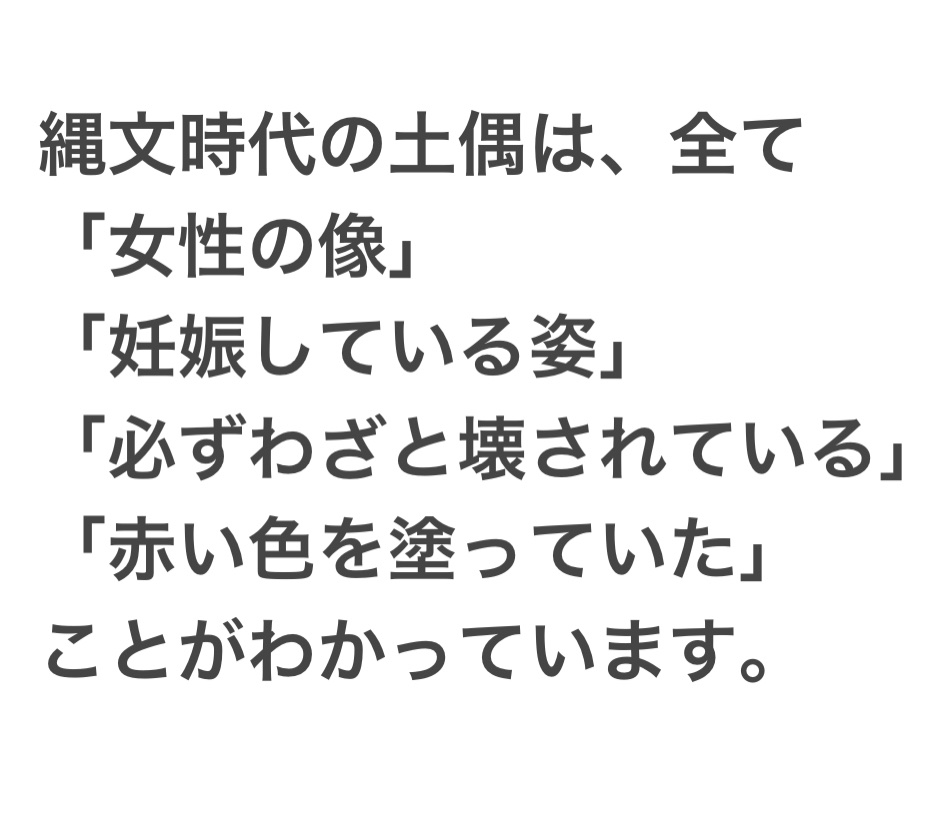
戦国時代では、武士が家を出発する際に縁起をかついで行う儀式がありました。
出征の当日は、一連の決められた作法の通りに行動します。そして最後に家を出発するときに、盃でお酒を口に運んだあと、戦勝を祈願して、その盃を地面に叩きつけて粉々に壊します。
これは、盃に息を吹きかける事で自分の厄を盃に移し、さらに叩き割る事で厄祓いをするというおまじないです。
盃を別名「かわらけ」とも言うそうですが、現代でも日本各地の神社で、【かわらけ割り】と言う厄除けのおまじないとしての習慣が残されているそうです。

また、土偶が妊婦であるという点に注目します。
医学の発達した現代でさえ、女性が出産に臨むことは、命懸けの行為です。
ましてや、縄文時代には、現代に比較しても、かなり危険が多かったものと予想されます。
土偶は、出産時の母体に起きるかもしれないトラブルを、身代わりになって受けるために作られたと考えるのが、最も自然です。
赤い色で装飾されていたという点についても着目してみましょう。
赤い色で装飾されて、女の子の災厄を身代わりに受けるお人形として、私たちが真っ先に思い浮かべるのは「おひな様」です。

女の子が生まれた家では、毎年の3月にひな人形を飾り、それを女の子が結婚するまで続ける習慣があります。
このおひな様は、色々な種類が存在しますが、ほとんどが鮮やかな赤色の着物を着ています。
おひな様は、私たちが幼少期から親しんでいて、誰もが「お姫さま」と勘違いしています。しかし、おひな様は、お姫さまの災厄を身代わりに受ける代役です。
ここまでの推理を整理してみると、
土偶の正体とは、
①出産が今よりもずっと危険だった時代に、妊婦のトラブルを身代わりに受けるための人形として作られた。
②出産時に身代わりとして破壊された。
③土偶のたましいをなぐさめるために、おしゃれな装飾をほどこしていた。
④土偶は、現代のおひな様の風習のルーツの可能性がある。
もしもそうだとしたら、土偶は縄文時代の人たちから、「おひなさま」と呼ばれていたのかもしれません。

以上、土偶の正体を推理してみました。